ステーブルコインって何?ビットコインとの違いや主な種類や使い道を解説
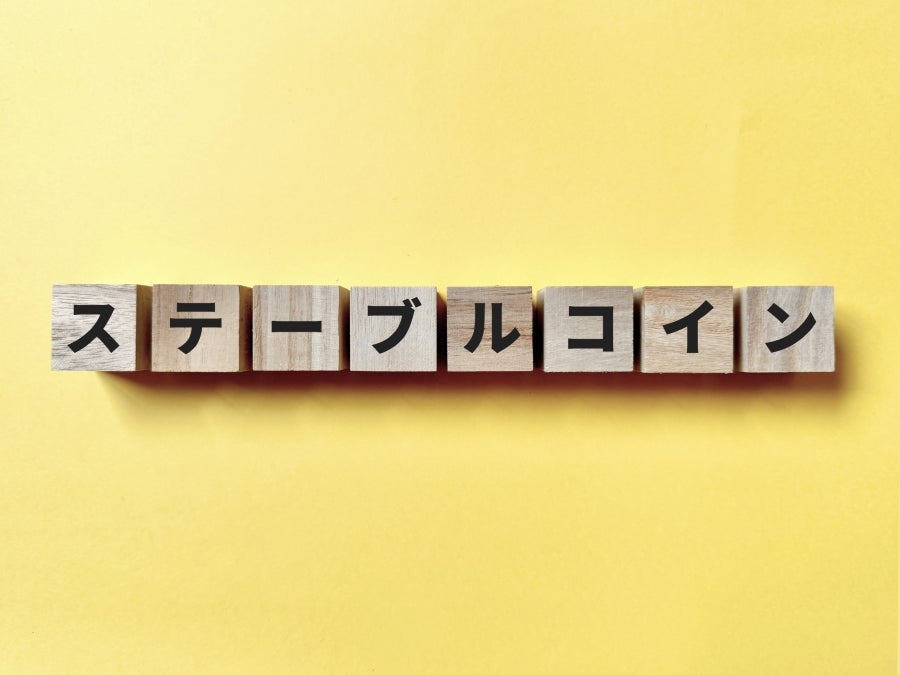
画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/33637708
この記事では、ステーブルコインと一般的な仮想通貨との違い、主な種類や使い道などをわかりやすく解説。10月27日に発行されたJPYCについてもお伝えします。
#ステーブルコイン #投資 #資産運用 #仮想通貨
ステーブルコインとは?

画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/24690012
「ステーブルコイン」とは、「stable(安定した)」の名前の通り価格が大きく変動しないように設計された仮想通貨です。法定通貨や現物資産などと連動するように設計されており、たとえば米ドルに連動するステーブルコインは1コイン=1ドルの安定した価格を保ちます。
ビットコインなど従来の仮想通貨との違い
ビットコインなどの従来の仮想通貨は、ブロックチェーン上で発行・取引をおこなうため、取引が迅速で手数料も安いという利点があります。ただし、市場の需給によって価格が大きく変動するため、日常的な決済や送金などには不向きです。
そこで登場したのが、価値を一定に保つよう設計されたステーブルコインです。価格が安定しているメリットを生かし、日常の送金や決済手段として利用が広がりつつあります。
電子マネーとの違い
法定通貨と同じ価値を持つデジタル決済手段には「電子マネー」もあります。電子マネーは企業が発行し、日本円などの法定通貨をそのままデジタル化したもので、代表的なものに『Suica』や『PayPay』があります。
電子マネーの中には同じサービス利用者同士で送金できるものや税金・公共料金の支払いに対応しているものもありますが、基本的には発行企業の加盟店やサービス内でしか使えません。
一方、ステーブルコインは企業が発行するタイプだけでなく、特定の管理者を持たない分散型のものもあります。ブロックチェーン技術を利用することで、国やサービスの枠を超えて世界中に送金できるのが特徴で、個人間送金や決済手段として活用の場が広がっています。
ステーブルコインの主な種類
ステーブルコインには、主に次の3種類に分けられます。
- 法定通貨担保型
- 暗号資産担保型
- アルゴリズム型(無担保型)
それぞれの特徴や代表的なコインを見ていきましょう。
法定通貨担保型
現在もっとも広く使われているのが「法定通貨担保型」のステーブルコインで、代表的なコインに『USDT(テザー)』や『USDC(USDコイン)』があります。このタイプのステーブルコインは、発行元が米ドルなど裏付けとなる資産を実際に保有し、その金額と同じ分のコインを発行します。
たとえば、1USDCを発行する際は、1ドルを準備金として保管します。こうした仕組みによって価格の変動を抑え、常に「1コイン=1ドル」という安定した価値を保てるよう設計されています。
暗号資産担保型
「暗号資産担保型」のステーブルコインは、法定通貨の代わりに『イーサリアム』などの仮想通貨を担保にして発行されます。代表的な例が『DAI(ダイ)』で、米ドルとほぼ同じ価値になるよう自動的に調整されています。
仮想通貨は法定通貨に比べて価格変動が大きいため、発行するコインより多くの担保が必要な「過剰担保」という方法が多く取られます。たとえば、100ドル分のDAIを発行するには、130ドル以上のイーサリアムを預ける必要があります。
アルゴリズム型(無担保型)
「アルゴリズム型(無担保型)」は、法定通貨や仮想通貨といった担保資産を用意せず、アルゴリズムの制御によって価格の安定を保つステーブルコインです。代表的なものに『フラックス(FRAX)』や『ニュートリノUSD(USDN)』があります。
これらは、需要が高まったときに新たにコインを発行して需要が減ったときには市場から回収することで、供給量を自動で調整して1コイン=1ドル程度の価値の維持を目指します。ただし、担保資産がないぶん価格の安定性には課題があります。
ステーブルコインの主な使い道
ステーブルコインには「取引が迅速で手数料が安い」「価格が安定している」というメリットがあることから、次のような使い道に注目が集まっています。
- 仮想通貨取引の一時避難先
- 海外送金
- 決済手段
- 資産運用
それぞれの使い道について詳しく見ていきましょう。
ステーブルコインの使い道①仮想通貨取引の一時避難先
ステーブルコインは価値が安定していることから、仮想通貨取引の一時的な避難先としてよく使われます。
たとえば、ビットコインなどの価格が大きく動いているときに一時的にステーブルコイン(USDTやUSDCなど)に交換しておけば、急激な値下がりの影響を避けられます。
ステーブルコインの使い道②海外送金
従来の海外送金は複数の銀行を経由することが多く、手数料が高いうえに着金まで数日かかるのが一般的でした。
ステーブルコインを使えば、銀行などの仲介機関を介さずにブロックチェーン上で直接相手に送金できます。手数料を大幅に削減できるうえ、送金も数分から数時間ほどで完了します。
ステーブルコインの使い道③決済手段
ステーブルコインは価格が安定しているため、ビットコインのように「受け取った直後に値下がりする」といったリスクが少ないのが利点です。そのため、海外ではステーブルコインで支払えるネットショップやサービスも増えています。
ステーブルコインの使い道④資産運用
ステーブルコインを使った資産運用で特に注目されているのが、銀行を通さずにお金を預けたり貸したりできる「DeFi(分散型金融)」という仕組みです。所有するステーブルコインを貸し出すことで、手数料が受け取れます。
ステーブルコインはビットコインなどの値動きの大きい仮想通貨と比べて暴落のリスクが少ないため、安心して長期的な資産運用に利用できます。
2025年10月27日 円建てステーブルコイン『JPYC』登場!
ステーブルコインの利用が世界的に広がりつつありますが、現在は米ドル建てのコインがメインです。そんな中、日本でも2025年10月27日に円建てのステーブルコイン『JPYC』が登場しました。
JPYCは、日本のフィンテック企業『JPYC株式会社』が発行するステーブルコインです。「1JPYC=1円」という価値を保つよう設計され、裏付けには銀行預金や日本国債など安全性の高い資産が用いられます。
JPYCの購入方法は銀行振込で、代金を支払うとデジタルウォレットにJPYCが送付されます。まずは企業間での決済用途が中心ですが、今後は個人間での送金や日常の買い物など幅広い場面での利用が期待されています。
参考:【国内初】日本円ステーブルコイン「JPYC」および発行・償還プラットフォーム「JPYC EX」を正式リリース
ステーブルコインの今後の動向に注目!

画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/4308312
ステーブルコインの登場により、送金や決済のあり方は今後大きく変わる可能性があります。実用化が進めば、手数料や時間の制約が少ない新たな手段としてビジネスや個人取引の効率化にもつながるでしょう。
日本でも円建てステーブルコインの発行が始まり、デジタル通貨の環境整備が進みつつあります。今後の制度や技術の動向に注目してみましょう。